ゲイムマンのダイスステーション
日本縦断ゲーセン紀行
123.港の博物館
〜静岡編(9)〜
スタート時点での「ゲーム路銀」は、「ゲーセン」にちなんで¥5,000(G千)。
ゲーセンでゲームをプレーして、1面クリアーするごとに、
「ゲーム路銀」は¥100ずつ増える。
(ただし、1プレー¥50円のゲームなら¥50ずつ、1プレー¥200なら¥200ずつ。
ゲームをプレーするためのお金も、「ゲーム路銀」からねん出する)
この「ゲーム路銀」だけを交通費にして、日本縦断を目指すのだ!
(前回までのゲーム路銀 ¥7,965)
| 清水 |
今年は東海地方の梅雨明けが8月3日と遅く、
梅雨が明けてようやく出かけられると思っていたら台風接近。
台風が過ぎたら行こうと考えていたら、今度は地震発生。
静岡は震度6弱で、その後も余震があったので、さらに出発を遅らせるはめに。
2009年8月17日。静岡に入ったのは午後6時25分。乗り継ぎが良く、予定より早く入れた。
 |
翌18日。ホテルの高層階から窓の外を見る。 よく晴れている。 |
| 10時21分発の興津行きに乗る。 草薙で静岡鉄道に乗り換えて新清水へ。 10時45分、今回のスタート地点、新清水駅着。 |
 |
10時53分、三保車庫前行きのバスに乗る。
三保には前回も行ったが、富士山が見えなかったので、
今度こそ松原越しの富士山を見たいと思ったのだ。
 |
 |
中央分離帯のある広い道路をバスは走る。かつてここには路面電車が走っていたようで、
村松バス停の先、車窓左手に、当時の電車や客車が置いてあった。
(写真は、帰路にバスの中から撮ったもの)
11時13分、三保松原入口で降りた。(ゲーム路銀 ¥7,965-¥320=¥7,645)
御穂神社に参拝し、松原へ向かおうとしたとき、
地元の歴史好きのおじさんが話しかけてきた。一緒に松原へと向かう。
御穂神社には約340年前、雷が落ちて火事になり、その後社殿が再建されたのだが、
松の木々の太さから考えて、最も古い松でも樹齢はせいぜい300年くらいなので、
松も火事でいったん焼けて、その後に地元の人々が植えたものではないだろうか、
というのがおじさんの説。
 |
おじさんいわく、松原がひらけ、 海がわずかに見えるこのあたりが、 三保いちばんの絶景とのこと。 確かに。 |
 |
羽衣の松の根元に、 羽車神社という小さなほこらがある。 御穂の神様が夫婦で羽車に乗って 羽衣の松に降臨したことから、 縁結びの神とされる。 |
おじさんの話では、この神社のことがネットで広まったようで、
願い事を書いた石が、一時期は鳥居の上まで積み上がったそうだ。
また、10月の羽衣まつりで上演される能「羽衣」は、
まさにこの木の根元に舞台を組んで披露されるという。
普通の能舞台とは違った、独特な雰囲気だそうだ。
| おじさんと別れて、海岸へ出てみたが、 こんなに晴れているにもかかわらず、 結局、富士山は見えなかった。 海の向こうの伊豆半島は うっすらと見えたのに。 |
 |
売店で、バニラミルクソフトを買ってひと休み。
冷たいお茶がつくのが、静岡らしくていい。
お店の方にうかがったところ、春や夏に富士山が見えることはめったにないらしい。
目的は達成できなかったが、地元の方のお話をうかがうことができたので満足。
12時47分発のバスに乗る。午後1時1分、波止場フェルケール博物館で降りた。
(ゲーム路銀 ¥7,645-¥290=¥7,355)
| フェルケール博物館に入る(入館料¥400)。 正式名称を「清水港湾博物館」といい、 清水港の歴史を学ぶことができる。 お金が後から戻るタイプのロッカーに 荷物を入れて、身軽に見学。 |
 |
まず最初の部屋は、清水港の概要。
江戸時代までは廻船の港で、1878年(明治11年)に波止場が造られ、海外貿易が始まる。
1899年(明治32年)開港場となり、1906年(明治39年)、日本郵船の神奈川丸が入港。
清水からお茶を直接アメリカへ輸出できるようになった。
昭和初期までの輸出品は、お茶、木材、マグロ缶詰だったが、
現在は自動車などの輸送機械が中心。
輸入は、木材、石油、ボーキサイト、豆、コーン、小麦、冷凍マグロ等。
この展示室には、港全体の地図や、
コンテナターミナルと、昭和初期の港の、大きなジオラマが並ぶ。
船につけるライトや信号旗、港を造る際に使われた潜水服や作業用具なども展示。
次の部屋は、荷役作業と漁業に関する展示。
昭和前半の荷役作業員の写真や、ネコ車、とび口(木材を運ぶ鉤つきの棒)、現場監督の服。
清水港に保存されているテルファークレーンが、現役で使われていた時の写真もある。
もっこ、麻袋、いろいろな手鉤、大八車、いろいろなハッピ。
輸出用の茶箱には、福助の絵が描かれている。
旧清水港線の、巴川口駅の風景を再現したジオラマもあった。
漁業関係の展示は、地びき網、漁船、びく、かご、はえなわの浮標(大きなガラス玉)、
マグロやサメ用の包丁など。
清水では真珠の養殖も行なわれていたらしく、その資料もあった。
この部屋から外へ出ると、洋風下見板張りの小さな建物がある。
清水食品という会社の、創立時の本社だという。1929年(昭和4年)のもの。
ここは日本で初めて、マグロの缶詰を商品化して輸出した企業だそうだ。
建物の中は、缶詰記念館となっていて、さまざまな時代のラベルや、製缶機械の模型、
この建物の前で創立当初の全従業員が並んで写っている写真、昭和前半の作業風景の写真、
缶詰用にマグロをカットする包丁や、果物を切る器械などが展示されていた。
フェルケール博物館のホームページはこちら
本館に戻る。通路に、矢澤利子さんという方の油彩画が展示されていた。
ぐにゃりとゆがんだパリの街並みが幻想的。
田宮千穂さんというジュエリー作家の作品も並んでいる。
次の部屋は、江戸時代の廻船について。
白い帆が張られた船の模型がずらりと並ぶ。模型といってもかなり大きい。
周りの壁沿いに展示されているのは、さまざまなロープの結び方、
海王丸のマストの一部、輸出用みかんの箱、
船だんす、茶箱のラベル。国内向けの茶箱は、昔、私のウチにもあった。
清水港線の写真、各時代の静岡鉄道の写真、
清水港線で使われたタブレットや切符切り鋏、
静岡鉄道の正面行先票と、かつて清水を走っていた路面電車の路線図。
思わぬところで鉄道資料が見られてうれしい。
清水港に、昭和4年に入港した第一艦隊と、昭和13年に入港した戦艦長門の、
絵や模型も展示されていた。
2階は企画展の「浜田知明展 −熊本県立美術館コレクション−」。(9月6日まで)
静岡空港が開業し、熊本空港との便が就航したことを記念して、
熊本県立美術館所蔵作品の展示が企画されたようだ。
浜田知明(ちめい)氏は、熊本県出身の版画・彫刻家。
戦地での体験を前衛的に描いた「初年兵哀歌」シリーズは、
写実的でない部分に、情感・情念が表れているように思う。
ご本人のコメントもあわせて展示されている。
「噂」「情報過多的人間」「風化する街」など、風刺の中にユーモアが効いた作品が多い。
「ややノイローゼ気味」から「何とかなるさ」にかけての作品では、
人間の心理って、こういう形で表現できるものなのかと驚いた。
フェルケール博物館のホームページはこちら
じっくり見ていたら時刻ははや3時28分。この博物館に2時間以上いた。
次の場所へ向かおう。
| またまたエスパルスドリームプラザにやってきた。 ここで昼ごはんを食べよう。 |
 |
 |
テルファークレーンの向こうに、 ウォーターボールや、 スーパーマリオのフワフワが並んでいた。 |
ドリームプラザの建物の中は、平日の昼間ながら、随分にぎわっている。
サッカーかフットサルの帰りとみられるお子さんが多い。
 |
観覧車の真横にある喫茶店で、 ナシゴレンを食べた。 上がっていくゴンドラの切れ間から、 港を行き交う船がよく見える。 ナシゴレンもうまかった。 |
木彫りのパルちゃん(清水エスパルスのマスコット)が置かれている
サッカーショップでストラップを購入した後、
1階へ戻り、清水すしミュージアムに入った。(8月31日まで入館料¥100。通常は¥300)
入口に、富士山の形に盛りつけられた握りずしサンプルと、
サミット各国首脳の似顔のすしがある。
エスカレーターで2階に上がると、迫力のあるマグロのはく製が展示されていた。
江戸時代のすし屋台が再現されている。
当時の握りずしのサンプルもあるが、今のすしよりべらぼうに大きい。
すしダネも、酢漬けや、しょう油で煮るなどの処理がされていたという。
合わせ酢は、今より酢が少なく、塩が多かったらしい。
浮世絵などに描かれたすし屋、全国のすし駅弁・空弁の箱を見て、さらに奥へ。
江戸時代の町並みを模した通りになっている。トイレの入口は銭湯風。
蓄音機、幻灯機、時計といった、文明開化時にもたらされたものも。
本格的にミュージアムらしくなるのは、「鮨学堂」と名づけられた部屋。
まずは、すしの歴史。タイ、ラオス、中国の雲南あたりで、
川魚に塩と米を混ぜ、米の乳酸発酵で保存したのが、すしの始まりらしい。
日本には中国から、奈良時代には入っていたとされる。
もともとは原形に近い「なれずし」だったが、
室町時代頃から、発酵用だった米を一緒に食べるようになり、
発酵の途中で食べることから「生成」(なまなれ)と呼ばれた。
魚の種類も多様化し、各地で特産の魚を使ったすしが作られるようになる。
江戸時代、すしの即製化が試みられ、この過程で酢が使われ始め、
やがて、熟成させずに酢をかけた「早ずし」が誕生する。
姿ずし、押しずし、巻きずし、ちらしずしなど、さまざまな形態のすしが現れる。
江戸後期には、稲荷ずし、そして握りずしが生まれた。
握りずしが一般的となったのは、華屋與兵衛の成功によるところが大きいという。
(現在の同名のレストランチェーンとは別)
江戸時代の握りずしでは、さっぱりしたコハダやアジが好まれ、
脂が多く、また産地が江戸から遠くて鮮度が落ちるマグロは嫌われていたらしい。
しかし江戸後期、伊豆や相模で大漁となり、「ヅケ」が作られ人気を博した。
それでもトロは使われず、トロが食べられるようになったのは、
20世紀に入ってかららしい。
歴史解説のほかに、この鮨学堂に展示されているのは、
すしネタの漢字、たくさんの種類の握りずしのサンプルなど。
浄瑠璃『義経千本桜』の、「すし屋の段」についても解説されていた。
源平の戦いのさなかに死んだはずの、平家の武将・平維盛は、実は生きていて、
弥助と名を変え、奈良・吉野の釣瓶ずしというすし屋で働いていた。
維盛をかくまった主人・弥左右衛門の娘・お里は、弥助に恋心を抱いていたが、
兄の無法者、いがみの権太が、弥助の正体を知ってしまう……。
「すし屋の段」は吉野の話なので、清水とは直接関係ないが、
平家の残党を探しに来た源氏の武将として、
史実では後に清水の狐ヶ崎で戦死する、梶原景時が登場する。
ちなみに、釣瓶ずしは実在するすし屋で、今でも営業しているらしい。
エスパルスドリームプラザのホームページはこちら
すしミュージアムを出る。時刻は午後5時48分。ちょっと中途半端だ。
今回もまた、3階のゲーム・アミュージアムに行ってみた。
「5機設定 EASY」と書かれていたので、
『レイクライシス』というシューティングゲームをプレイ。
当たり判定がいまいちよくわからないまま、2面のボスでゲームオーバー。
ゲーム路銀の増減なし。
最近MONDO21で、ゲーマー・中野龍三さんの
『シューティングゲーム攻略軍団参上!』という番組を見ているが、
私が中野さんのようになるのは難しいようだ。
で、今回も『ビシバシチャンプオンライン』のオフラインモードをプレイ。
何と11面クリアし、エンディングを見ることができた!
サッカーのドリブルを題材にしたゲームと、おでんの串刺しゲームが
とりわけうまくいった。
静岡市にいるからではないだろうけど。
(ゲーム路銀 ¥7,355+¥1,000=¥8,355)
「スコール」という珍しい缶ジュースを買って飲む。乳性炭酸飲料。
宮崎の都城で作られているらしい。
6時45分になった。少し早いが、晩ごはんにしよう。
さっきのすしミュージアムの隣にあったすし屋さんへ。
中トロ、赤身、生しらす、生桜えびなど、地のものをたっぷり堪能。
エスパルスドリームプラザのホームページはこちら
日の出ドリームパーク(清水港 日の出地区)のホームページはこちら
宿泊地が静岡駅の近くなので、ここから無料バスで清水駅まで行こうと思ったが、
バス停に着いたのが7時35分。平日のバスは30分間隔で、次は8時ちょうどまで来ない。
| 路線バスに乗ろう。 波止場フェルケール博物館バス停まで歩く。 浪漫館という建物のステンドグラスが目立つ。 |
 |
明日の旅はここから再開しよう。
7時50分のバスに乗り、清水駅から電車で静岡駅へ戻った。
¥8,355
今回のルート
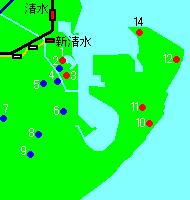 |
1.エスパルスドリームプラザ 2.清水次郎長の船宿・末廣 3.フェルケール博物館 4.清水次郎長生家 5.梅蔭寺 6.清水総合運動場 7.清水船越堤公園 8.龍華寺 9.日本平運動公園・アウトソーシングスタジアム日本平 10.三保の松原・羽衣の松 11.御穂神社 12.清水灯台・三保飛行場 14.東海大学海洋科学博物館・自然史博物館 |
静岡観光コンベンション協会(静岡市・焼津市・藤枝市・島田市)
富士山観光交流ビューロー ハローナビしずおか(静岡県)
JR東海 静岡鉄道
次回、「日本縦断ゲーセン紀行 124.静岡編(10)」では、
清水次郎長ゆかりの場所を巡る。
「日本縦断ゲーセン紀行 122.静岡編(8)」に戻る
「ゲイムマンのダイスステーション」タイトルページに戻る
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|