ゲイムマンのダイスステーション
日本縦断ゲーセン紀行
50.幕末を生きた人々
〜福島編(6)〜
スタート時点での「ゲーム路銀」は、「ゲーセン」にちなんで¥5,000(G千)。
ゲーセンでゲームをプレーして、1面クリアーするごとに、
「ゲーム路銀」は¥100ずつ増える。
(ただし、1プレー¥50円のゲームなら¥50ずつ、1プレー¥200なら¥200ずつ。
ゲームをプレーするためのお金も、「ゲーム路銀」からねん出する)
この「ゲーム路銀」だけを交通費にして、日本縦断を目指すのだ!
(前回までのゲーム路銀 ¥12,240)
| 会津若松 |
| 2005年12月4日。 ホテルチェックアウトの際に福引きがあり、 何と50個に1個しかない当たり玉を引き当てた! 金貨ゲット。 バスの時刻まで間があるので、 今日もハンバーガー屋さんで朝食。 雪は降っていない。 (写真は、駅前地下通路の入口) |
 |
9時25分のバスで、飯盛山へ(ゲーム路銀 ¥12,240-¥200=¥12,040)。
昔の看板が展示される神禧堂薬館や、会州一蔵品館など、市街地にある古い建物の前を通る。
ちょっと遠回りなルートだったので、目的地に着いたのは9時40分。
 |
旧滝沢本陣横山家住宅である。 雪がこんもりと積もっていて、 おととい来たときとは違う景色になっていた。 (入場料¥300) |
ここは歴代会津藩主が、参勤交代などのときに立ち寄って旅支度を整えた場所。
戊辰戦争時には大本営となり、
あの白虎隊(士中二番隊)はここから出陣した。
国重要文化財にして、文部省史蹟。
入ったところは、武家というより典型的な古民家といった感じ。いろりもある。
しかしその奥に、一段高くなった「御座の間」があった。
遠州流の中庭もある。
この部屋の柱や障子枠には、そこらじゅうに、
戊辰戦争時の弾痕や刀傷があり、血なまぐさい歴史を今日に伝えている。
一方、案内テープの声は、会津なまりの素朴なもので、
途中で紙をめくる音まで入っている。
素朴な農家の様子と、戦乱の歴史と、両方が混在する、不思議な史跡だった。
 |
続いて向かったのが、白虎隊伝承史学館。 (入館料¥300) 個人が運営する小さな博物館だが、内容は充実。 |
幕末を生きた、さまざまな人物の写真が展示されていたのが印象深い。
会津藩士、新選組、娘子隊、奥羽越列藩同盟、西軍(新政府軍)方と、
数多くの人が、それぞれの立場で戊辰戦争にかかわり、
また生き残った人々が、明治時代いろんな分野で活躍したことがわかり、興味深い。
ほかにも、会津藩で使われた刀のつばや、白虎隊の脇差、鏡や器などの日用品、
東西両軍の銃などが展示され、内容の濃い資料館だった。
館長さんの熱意がすごいなあと思う。
| いよいよ飯盛山の参道へやってきた。 階段と、その隣にはスロープ状のエスカレーターがある。 |
 |
 |
上る前に、階段下にある 白虎隊記念館へ(¥400)。 |
こちらは広いスペース。
日新館の教科書に始まり、各種の銃や陣羽織、
白虎隊士で後に東京帝大総長となった山川健次郎の書、
自刃した隊士・津川喜代美の手紙、自刃するも一命をとりとめた飯沼貞吉の書、
近藤勇の鉢がね、島田魁の新選組袖章、
娘子軍(じょうしぐん)隊長として戦い、戦死した中野竹子の書、
西軍諸将の書などなど。
秋篠宮妃殿下の曽祖父・池上四郎も、鶴ヶ城で籠城を経験したそうだ。
| 生還した白虎隊士、酒井峰治の手記もあった。 彼は退却のとき隊からはぐれてしまったが、 農民・庄三に発見されて、無事生還できたそうだ。 記念館前の像は、峰治が愛犬クマと再会したところ。 峰治はクマの道案内で、鶴ヶ城に入城できたという。 |
 |
日新館の様子や、滝沢本陣からの白虎隊の出陣、
煙に包まれる城を、飯盛山から眺める白虎隊士の姿などが、人形で再現されていた。
2階には、第二次大戦時、京都、鎌倉、奈良、そして会津を爆撃から救った
ウォーナー博士に関する資料や、
『荒城の月』を作詞した土井晩翠の資料、
徳富蘇峰に関する資料など。
(この記念館の創立者・早川喜代次氏は、蘇峰の顧問弁護士だったそうだ)
 |
白虎隊記念館のホームページはこちら。 |
時刻は12時15分。いよいよ白虎隊自刃の地へと向かう。
エスカレーターに乗っても良かったが、乗らずに階段を行こう。
これくらいの階段なら、過去に何度も上っている。
雪解け水が、木の上からポタポタ落ちてくる。
途中、息を切らして小休止するが、根性で上りきった。
小さな広場の周りを、さまざまな碑がぐるりと囲んでいる。
禁を犯して白虎隊士の遺体を埋葬した肝煎・吉田伊惣次氏篤志の碑。
(函館の碧血碑にも、似た話があったなあ)
亡くなった女性たちをまつった、会津藩殉難烈婦の碑。
| 昭和3年にローマ市から贈られた碑(写真)や、 昭和10年、ドイツ大使館フォンエッツドルフ氏寄贈の碑、 会津藩とともに戦った、郡上藩凌霜隊之碑など。 |
 |
そしてこの広場の奥に、白虎隊士たちの墓があった。
今も参拝者が絶えず、線香の匂いがする。
墓は明治23年に建てられた。
19人それぞれの名前が刻まれた、19の小さな墓石が並んでいる。
右側には、会津の各地で戦死した白虎隊士31名の墓が、同じ形で並ぶ。
左側には、各地で戦死した、白虎隊と同年代の会津少年武士の慰霊碑がある。
背後の木立と、抜けるような青空が、あまりにさわやかすぎて、切ない。
小道に入り、飯沼貞吉の墓を拝む。
そしてその先に、まさに白虎隊が自刃した地があった。
意外なことに、周囲を一般の墓地に囲まれている。
| 確かに鶴ヶ城は見えたが、思いのほか遠い。 (写真では黒くシルエットになっている。 中央やや右寄りに天守閣) もっとも、当時は天守閣の周りにも建物があって、 それらも含めて鶴ヶ城だったのだから、 今とはちょっと眺めが違っていたのかもしれない。 |
 |
白虎隊は、15〜17歳の少年たちから成る。
ここで亡くなったのは、白虎隊の中でも、身分の高い武士の子息から成る士中隊だった。
白虎士中隊は、松平容保を護衛して滝沢本陣にいたが、
戦線が近くの戸ノ口原まで迫っていたため、
一番隊を本陣に残し、二番隊が援軍として現地に向かった。
しかし着いた頃には既に勝敗がほぼ決しており、二番隊も散り散りになってしまう。
残った17名(諸説あり)は、城に戻って最後まで戦うべく、
かんがい用の水路を通って飯盛山までたどり着く。
だがまさにこの場所で、城下が炎に包まれているのを見て、城が落ちたと思い、
意を決して全員が自刃した。
ただ1人、飯沼貞吉だけが一命をとりとめ、彼の証言によって
この白虎隊の悲劇が、後世に語り継がれることになった。
他の場所で自害した隊士も含め、現在では19名がまつられている。
土産物屋さんでお茶を買い、景色を見ながら飲む。
白虎隊がこの景色を眺めたときの心境を考えると、
単なる楽しみでここを眺めるのも、申しわけないような気がする。
いや、彼らのような先人たちの働きがあったからこそ、今の平和が築かれているのだ。
だったらこうして景色を楽しめるほどの平和を、大いに享受すべきではないだろうか。
……そんな勝手な解釈で、強引に自分を納得させた。
 |
「さざえ堂」とよばれる建物へ行く。 国の重要文化財。 正式には「円通三匝堂」(えんつうさんそうどう)という。 説明板によると、この建物は、 「1.上りも下りも階段がない 2.1度通った所は2度通らない」 ということだ。 中に入ってみた(拝観料¥400) |
| 寛政8年(1796年)建立とされる。 高さ約16メートル。 かなり急だが、確かに階段ではなくスロープだ。 |
 |
昔は三十三観音が安置されていたらしいが、
明治以降、皇朝二十四孝の絵になった。
それらの絵を見ながら、右回りのらせんスロープを上り、
折り返して左回りの下りとなったが、
確かに、同じ絵を一度も見ることなく、地上に出てきた。
不思議。
さざえ堂のホームページはこちら。
| 坂を下りると、小さな神社があり、 その脇に、「戸ノ口原の洞門」が口を開けていた。 白虎隊が戸ノ口原から引き揚げる際に通ったそうだ。 多量の水が流れる水路で、 人が通るにはあまりにも小さい。 中は暗くて、どうなっているかわからない。 よくこんな所を通ったものだ。 |
 |
坂を下りてまっすぐ行くと、さっきの白虎隊伝承史学館の前に至る。
私は途中で左に折れ、太夫桜とよばれる、大きな桜の木の前を通過。
白虎隊記念館のほうに戻ってきた。
飯盛山下バス停到着、午後1時57分。
次のバスは2時11分。次の列車が2時46分なので、ちょうどいいくらいの時刻だろう。
バスはたいへん混んでいた。2時20分、会津若松駅着。
(ゲーム路銀 ¥12,040-¥200=¥11,840)。
ロッカーから荷物を出して、切符を買って、食べ物を買って、改札を抜ける。
郡山行き、新潟行き列車の出発を、相次いで見送る。
| 会津鉄道AT-550型。 |  |
 |
野口英世の母シカの手紙が、 前面にも側面にもラッピングされた「ふるさと列車」だ。 |
2時46分発車。こうしてまたひとつ、拠点とした町を後にする。
駅Cafeの七日町に停車。
左手、市街地の向こうに、山々がきれいに見える。サンドイッチを食べ終わる。
西若松停車。ここまでがJR、ここから先は第三セクターの会津鉄道だ。
駅舎は真壁造り(和風ハーフティンバー)の、新しいものだった。
西若松を出る。なおしばらく住宅地は続く。左の連山がきれい。
門田(もんでん)の手前でいったん家並みが途切れ、右側にも山が姿を現す。
ここが盆地ということがよくわかる。
門田を出たところに柿の木が並び、たわわに実をつけている。
| 門田−あまや間の車窓風景。 |  |
気がつくと、左の山々が間近に迫っていた。あまやを出ると、右の山もだんだんと近づく。
芦ノ牧温泉駅。懐かしい感じの木造駅舎。
ここもかつて、ミニ独立国「ジパング国会津芦ノ牧藩」だった所だが、
温泉が駅からちょっと遠いので、通過しますごめんなさい。
芦ノ牧温泉のホームページはこちら。
左が山、右が崖。山の中腹を通っている。
長いトンネルを抜ける。
 |
「秘境駅」としても知られる、大川ダム公園駅から見た風景。 ダム湖の若郷湖は、次の芦ノ牧温泉南駅からよく見えた。 このダムのために、会津線はルート変更が行なわれ、 駅も1つダムに沈んだらしい。 |
また長いトンネル。抜けて川を渡り、トンネル。
そのトンネルを出たところが湯野上温泉駅だった。
3時25分着。ここで降りた。(ゲーム路銀 ¥11,840-¥1,000=¥10,840)。
| 〜七日町(なぬかまち)〜西若松〜南若松〜門田(もんでん) 〜あまや〜芦ノ牧温泉〜大川ダム公園〜芦ノ牧温泉南〜 湯野上温泉(ゆのかみおんせん) |
 |
かやぶき屋根の堂々とした駅舎だ。 四方を山に囲まれている。 駅の中にはいろりがあって、火が入っている。 ひのきの大きなテーブルもあった。 |
駅の中でちょっとくつろごうと思ったが、気がつくと、さっきの列車がまだ止まっている。
これを見送ると、次の上りは午後4時台。
考えを変えて、この列車に、発車間際に飛び乗った。
この駅からは、湯野上温泉の温泉街が近いほか、
かやぶき屋根の建物が並ぶ、大内宿にも行くことができる。
大内宿にも行きたかったが、バス便がなく、行き帰りともタクシーなので、
ゲーム路銀のことを考えると、さすがにちゅうちょした。
湯野上温泉のホームページはこちら。
大内宿観光協会のホームページはこちら。
「あいLove会津」にも、大内宿の紹介がある。
3時33分発。大川が左側すぐ下に、続いて右側に見えるという、雄大な車窓風景。
| 38分、次の駅、塔のへつりで降りた。 (ゲーム路銀 ¥10,840-¥260=¥10,580) 駅名標には、イラストとともに、 「奇岩が招く藤娘」の文字が。 |
 |
| 塔のへつり |
| 森の中にある小さな駅。 ホームの端で、巨大なこけしが出迎える。 周りに人がいない。近くの道を、ときおり車が通り過ぎる。 |
 |
車道を歩くこと約3分。景勝地、塔のへつりにやってきた。
 |
大川沿いに、岸壁がそそり立つ。 私は以前来たことがあるが、そのときには、 岩が本当に塔のように林立していた。 今は全体が雪に覆われているので、 塔の形ははっきりしないが、 これはこれでまた、おもしろい景観。 |
 |
岩の下には溝があり、人が歩けるようになっている。 塔の中腹(写真左上)に、虚空蔵尊がまつられている。 さすがにこの雪では、歩く人もいないけど。 |
4時10分、駅に戻った。次の上りは4時22分。
駅舎内は暖房こそないが、案外寒さをしのげる。
踏み切りの警報機が鳴った。やってきたのは、
……AIZUマウントエクスプレス用車両、キハ8500系だ!
普通列車として運用されることもあるのか。
おかげで、リクライニングシートの座り心地を堪能できた。
左側、大きな窓から、崖の下を流れる大川が見えた。
トンネルを1つ抜けると川は消え、住宅地に。
また川を渡る。外は薄暗くなってきている。
会津下郷を出てすぐ、湖のように広くなった川を渡った。
田畑は雪に覆われていて、真っ白な平原と化している。
わずかにあぜ道の盛り上がりがあるので、かろうじて農地とわかる。
養鱒公園駅の先で、えらく複雑に分岐した川を渡る。
これは支流の加藤谷川(かどたにがわ)というらしい。のんびり走るキハ8500。
田島高校前駅の近くから、家が増えてきた。
 |
終点・会津田島着、午後4時51分。 (ゲーム路銀 ¥10,580-¥600=¥9,980) |
| 〜弥五島(やごしま)〜会津下郷(あいづしもごう)〜ふるさと公園 〜養鱒公園(ようそんこうえん)〜会津長野〜田島高校前〜 会津田島 |
 |
大きな会津田島駅。 駅全体が「ふれあいステーションプラザ」となっていて、 1階に近隣町村も含めた観光情報コーナー、 2階にはレストランがある。 コンベンションホールなどもある。 会津鉄道は、この駅から南側が電化されている。 |
もう日が暮れている。田島で行きたい場所もあるが、
次回またここからスタートすることにしよう。
うーん、2005年中に東北を出られなかったか。
5時14分の鬼怒川温泉行きに乗る。引き続き8500系。ただしさっきとは別の車両。
6時21分、鬼怒川温泉着。隣のホームに停車中の、
特急きぬ(スペーシア)に乗り換える。26分発。
 |
終点・浅草到着8時32分。 東武浅草駅名物、降り口の渡し板を渡った。 (東武浅草駅のホームは、先端がカーブしているので、 乗降口とホームの間があく。そのため、 お客さんが線路に落ちないように板が渡される) |
雷門の前から延びる道路に、浅草らしい祭りを描いたイルミネーションが輝いていた。
¥9,980
今回のルート
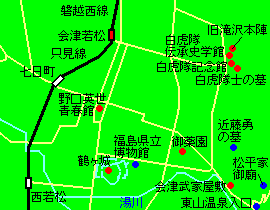
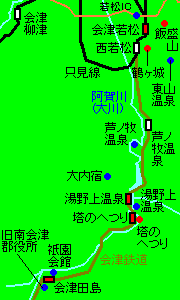
会津若松観光物産協会 下郷観光チャンネル 下郷町観光協会 南会津町のホームページ
あいLove会津 パーフェクトあいづ
福島の旅 JR東日本仙台支社 会津鉄道
次回、「日本縦断ゲーセン紀行 51.福島編(7)」では、
遂に念願の栃木県入り。
「日本縦断ゲーセン紀行 49.福島編(5)」に戻る
「ゲイムマンのダイスステーション」タイトルページに戻る
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|
| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |
|